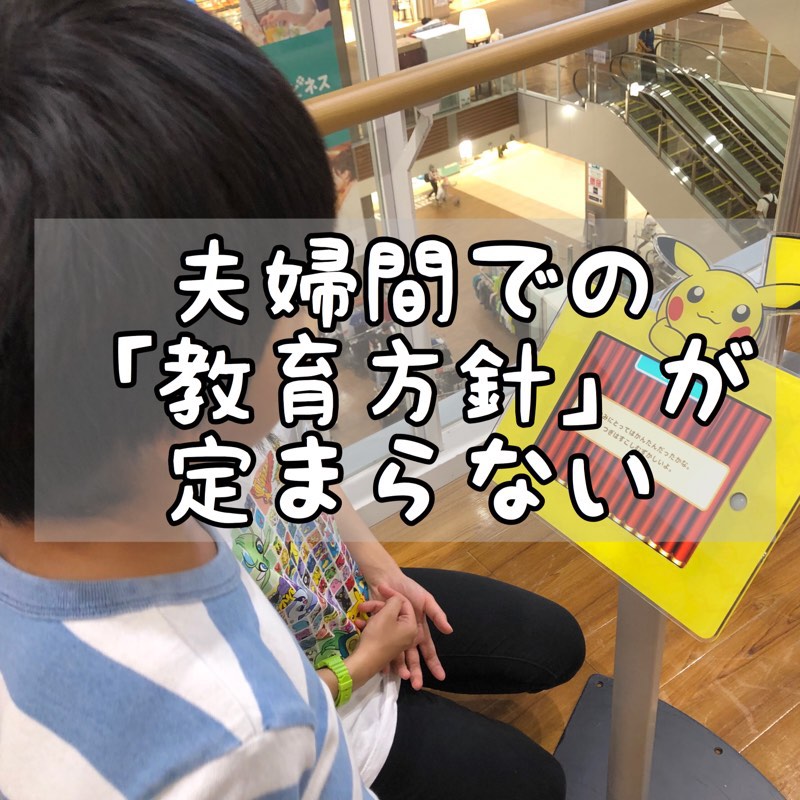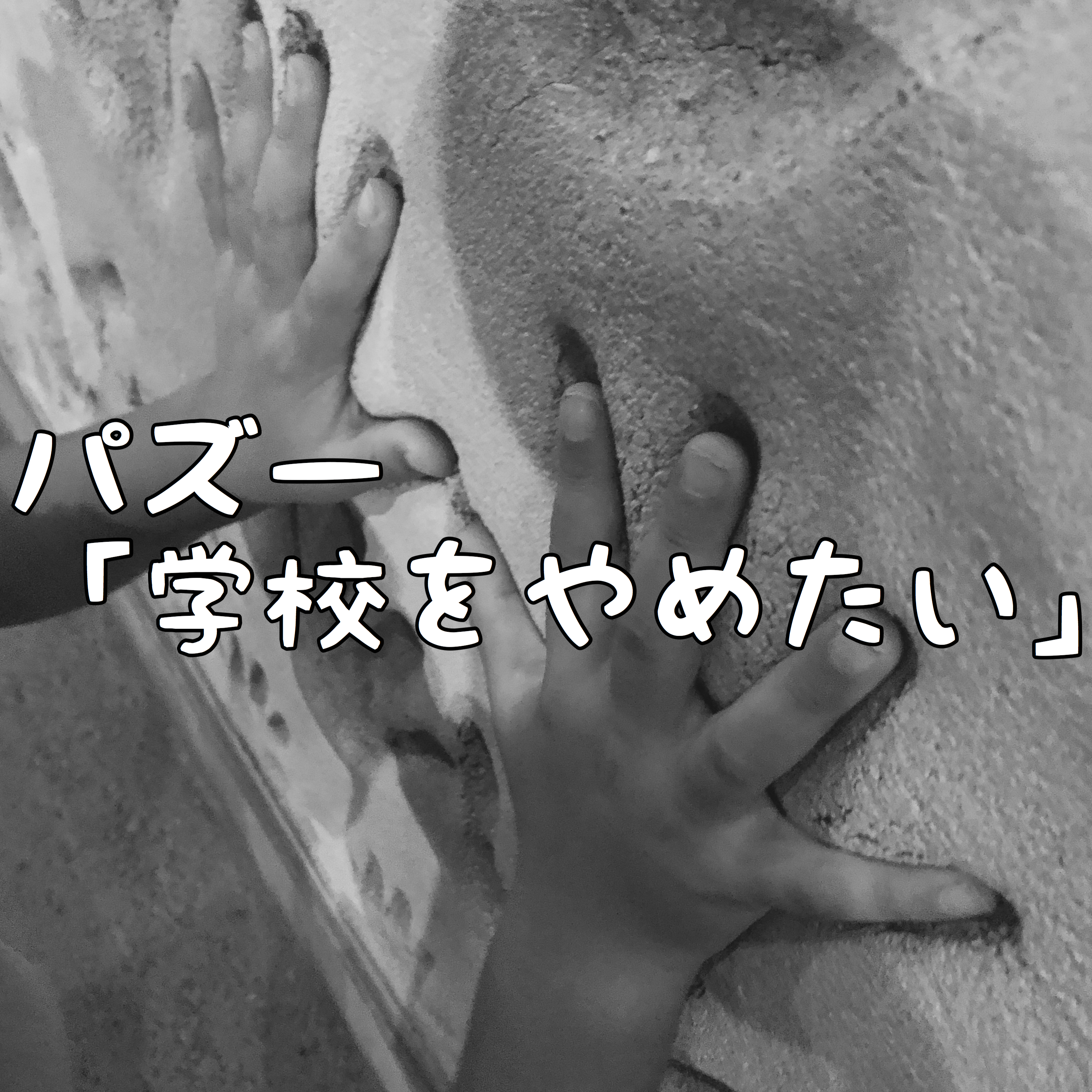(当時の)旦那さんと
ココとは教育方針が全く逆で
<パズー小学校入学前>
ココ(子供の意思が一番大事だし、
これからの時代を考えて
インターナショナルスクールに
通わせたい)
と思っていましたが、
当時はインターナショナルスクールに
通わせる経済力もなかった
事に加えて、
(当時の)旦那さんは大学まで
学費のかからない
【公立を卒業すること】
こそが成功であり
優秀という考え方でした。
夫婦の立場が
対等ではなかった
我が家では、
ココの意見などは
聞いてもらえませんでした。
さらに
(当時の)旦那さんは
とても教育熱心で
パズーが小学校へ入ってからは
家にいる時は
宿題を(鬼の形相でしたが・・)
手取り足取り教えたり
学校の用意も
全て(当時の)旦那さん
が子供が寝静まった後に
完璧に揃えてあげたり、
失敗を先回りして
防ぐのが教育だと思っている
考え方でした。
ココとしては、
学校の用意も
本人にやらせたい(自立)
宿題も多すぎて
「持ち帰り残業のようだな」
と思っていたくらいなので、
お互いの教育方針がそもそも
真逆な事に加えて
歩み寄りの話し合いも
出来なかったので、
夫婦で
折り合いもつかないまま
ココが教育に携われば
子供自身が
「パパとママで言っていることが違う」
と混乱すると思い、
教育に携われませんでした。
なので、
パズーと話しはするものの
「学校をやめたい」
というパズーの言葉を組んで
行動に移すといところまでは
いきませんでした。
今振り返れば
パズーの教育に
携われなかった期間
子供と距離があったのだと
思います。
それが別居を期に色々と
環境が変わっていきます。
続く
「学校をやめたい」と話す長男パズーとの日々 〜Vo.1〜
皆で整列して
授業を聞いてって
出来る子もいれば、
そこに「違和感」を感じる子もいる
全員同じなわけがない、
遺伝子が近い親子だって
全然違うのだから
そう感じる子が居ても
なんら不思議な事ではないと
ココは思っています。
一人一人感じ方も
得意も不得意も
あるのは当たり前。
だから学校に「違和感」
を感じる子が居ても
それはそれで
普通なのだと思うのです。
「学校」へ行かない
と言われると親としては
不安になるのですが、
親自身が「学校」についての
価値基準んであったり
目的が明確であれば
取捨選択が出来ますし、
子供にも「学校」へ行く意義に
ついて説明する事が出来ます。
漠然と年齢が来たら
「学校」に行くものと
思っているだけだと
学校に「違和感」を感じている
子供に対して説得力のある
説明ができません。
「学校」って何を学びに
行く所でどういう人間教育を
させるところなのか?
その成り立ちを考えたり
「学校」を卒業した後
最終的にどういう大人になる為の
基礎作りの場なのかを親自身が
考える必要があるのだと思います。
ただただ「学校」に行けば
時間がたてば大人になる
ではなくて
◯◯の学校では
こういう教育理念だから
将来こういう仕事に就ける、
まで考えて
今の「学校」選びが出来ていれば
子供に説明も出来ます。
私が子供の頃は
「学校」はお友達と遊ぶ場だったので
どちらかというと
好きでした。
なので、
特に「違和感」を感じたり
行きたくないという事も
ありませんでした。
今親になり子供を通して
「学校」を
みていると
当時と何一つ変わらない教育の
カリキュラムのままでした。
もちろん英語教育の導入や
今後はプログラミングなど
当時は無かった必修科目が
増えていくのですが、
けれでも、まだまだ
今の教育の変化のなさに
「違和感」を
感じました。
それに加えて
パズーも
一年生の頃から
「学校をやめたい」
と言っていました。
様子をみていると
お友達とトラブルがある
わけでもなさそうですし、
「学校に行きたくない」
とぐずった事も一度も
ありませんでした。
ただ思い立った時に
一貫して「学校をやめる」
という発言を繰り返していました。
最初は慣れない学校生活で
そんな発言をしている
ものだと思って
いたのですが、
二年生になっても同様に
「学校をやめたい」
と言い続けていました。
パズーが「学校をやめたい」
というたびに
色々話し合いました。
ココ「学校をやめて
家にいる間やりたい事が
決まったら良いよ」
パスー「カブト虫を飼う」
ココ「今飼っているバッタの世話も
やってないのに?」
パズー「・・・・・」
ココ「学校が嫌なら他の学校
に通う?」
パズー「ううん、通わない
学校をやめたいの」
ココ「嫌な子とか
いじめられたりしてるの?」
パズー「乱暴する子はいるよ。」
ココ「じゃ、その子と
話し合ってみようか?」
パズー「んー、そんなに
困ってないから大丈夫」
ココ「分かった、
じゃまた何かあったら教えてね」
パズー「うん、分かった」
と言って毎日学校へは
楽しそうにお友達と通うのですが、
「学校をやめたい」という
意思そのものはその後も
変わりませんでした。
続く